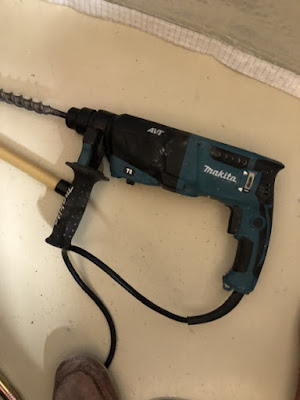ついてない(FSZ&750RS)

その1 FSZ編 バッテリーを新調して、1か月以上乗っていなかったFSZを久々に始動。この日は台風一過の快晴&気温も低め。久しぶりにEも助手席に乗ってくれて、早朝ドライブ。 新しいバッテリーの威力は大きく、セルの回りから違う。すぐに始動でき、冷間時からアイドリングも安定。旧車といえども電気で動いているんですよね。1~2分、路上で暖気して、出発。 うん、快調、快調。でも、暑くなる前に退散。バイパスを走って、前方信号が赤で止まると、少しガソリン臭が。ヤバそうな燃料ホースは交換したし、いったい何処から? 帰宅してガレージに入れると、やはり少しガソリン臭が。う~ん。暖気で止めてた付近の路面を見ると、オイル染みが。エンジン下部あたりなので、キャブから吹き返したガソリンがブロック伝ってオイルを洗い流した? キャブ周りをチェックしても、よくわからない。キャブ下側にガソリンは付いていなかったのですが、ガスケットのところからのガソリン滲みはソコソコ。前回キャブOHはエンジンOHの時、つまり2014年なので、10年前。これは、OHしろってことか? その2 750RS編 FSZの次は750RSも動かさねばと、前日に確認してみたら、こちらもバッテリーが放電しきっている(11.5V)。パルス充電で復活を試み、1晩充電しましたが、70%どまり(こちらも6年目なのでそろそろ寿命?)。まぁ、70%あれば、動かすことはできるので、近所を1周することに。 キャブが乾いているのか、始動までは少し難儀しましたが、掛かってしまえば快調そのもの。途中、給油すると、相変わらずの高燃費(涙)。ある意味安定しているので問題なし(遠乗りすればもう少し改善するし)。気になるのは、ブレーキ鳴き。やっぱりディスクが焼けちゃってるのかなぁ。 帰宅して、さらにバッテリーをチャージ。朝から晩まで12時間充電しても80%にしか充電できない。ってことで、新品買えってことか?